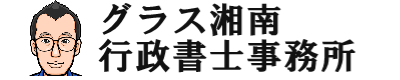宅建業免許の手続きの流れ

宅建業免許申請の手続きには、いくつかの手順を経なければなりません。
今回は一般的な申請手続きの流れを解説します。
事前準備として申請にはいくつかの要件をクリアする必要があります。前コラム「宅建業免許申請の5つの要件」を読まれていない方はまずはそちらをお読み下さい。
要件をクリアしていることを確認したら、申請書類の作成を行います。当事務所へご依頼頂ければ申請書の作成は勿論のこと、申請先への申請も代行して行います。主な申請書類については前コラム「宅建業免許申請に必要な書類リスト」をご参照下さい。
申請先については、1つの都道府県のみに事務所を設置する場合は、その事務所の所在地を管轄する都道府県知事に申請します。2つ以上の都道府県に事務所を設置する場合は、国土交通大臣に申請します。具体的には主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局を経由して申請します。
書類が受理されると、行政庁による審査が行われ、知事免許では大よそ30日~60日程度であり、大臣免許の場合は更に長くかかることがあります。審査中には、提出書類の補正や追加書類の提出を求められる場合があり、その分審査期間が延びてしまいます。
また、会社設立登記申請を含めると更なる期間が必要となりますので、注意して下さい。
審査が完了し、許可が下りると申請者の事務所宛に免許通知が届きます。
営業保証金の供託、又は保証協会への加入も必要になってきますが、こちらの申請のタイミングは、宅建業免許申請の後、速やかに行う必要があります。これは免許通知を待ってからでは保証協会の審査期間分、更に待たなくてはならず、営業開始時期がその分遅れてしまうからです。
営業保証金の供託は主たる事務所で1,000万円、その他の事務所で500万円を法務局に供託しなければならず、高額となります。ほとんどの業者は保証協会へ加入することになります。保証協会への加入では、弁済業務保証金分担金として主たる事務所で60万円、その他の事務所で30万円を納付します。
保証協会への加入申請後に、協会所属支部による事務所調査と面談があります。これは実際に協会の担当者が事務所を訪れ、事務所としての要件を満たしているかチェックします。面談は、事務所調査とは別日に行われるケースが多く、会社の代表者と専任の宅建士の同席を求められ、事業計画や経営方針等を確認されます。
その後、弁済業務保証金分担金やその他会費を納付し、免許通知と保証協会から送付される弁済業務保証金分担金納付済証を持参して、県土整備局事業管理部建設業課宅建指導担当へ行きます。
免許証を受領し、晴れて営業ができるようになります。
宅建業免許申請は行政庁の申請の他、保証協会加入手続きも併せて行わなければなりません。提出する書類も複雑であり、申請者ご自身で行うことは容易ではありません。
当事務所では宅建業免許申請の作成、代行申請を承っています。
まずは当事務所へご相談下さい。
お問い合わせは↓ここから
お問い合わせ