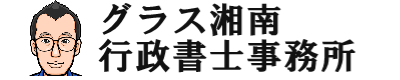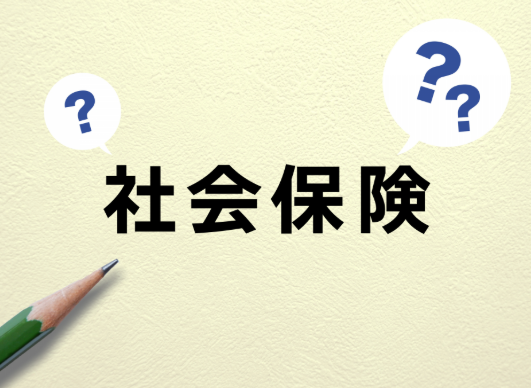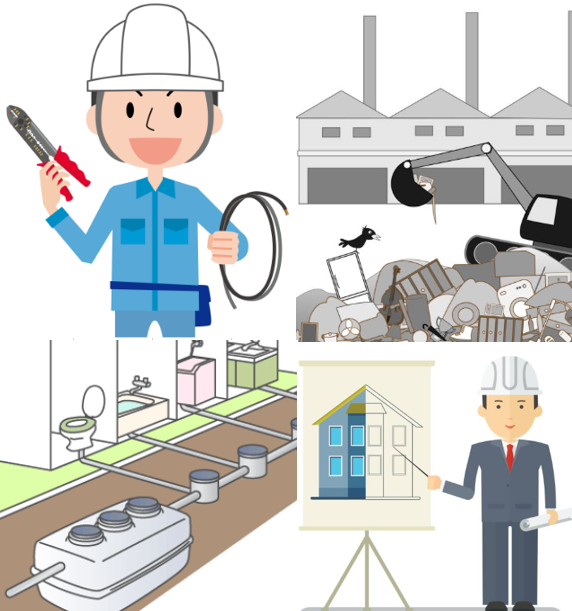個人事業主から法人へ!建設業許可切り替えについて
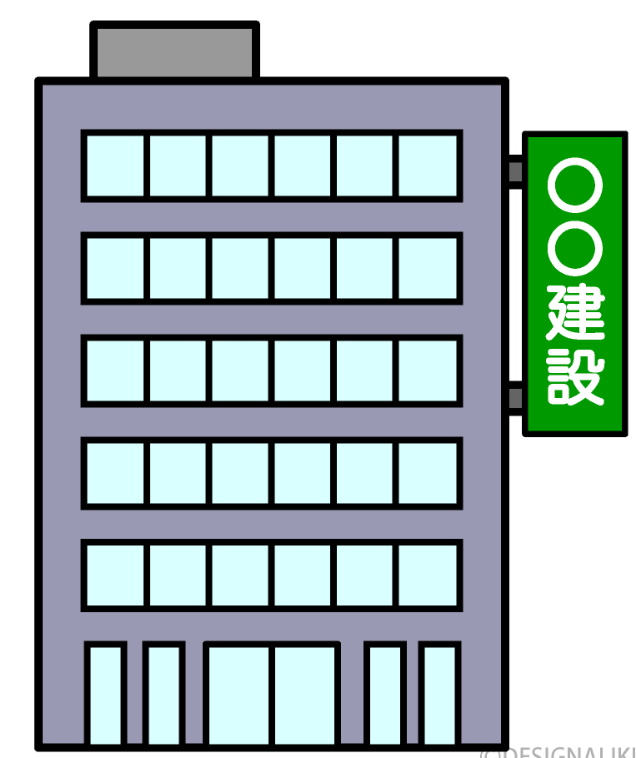
個人事業主として建設業許可を取得して経営も順調に進み、今後法人化をすべきかどうか悩まれている方もいらっしゃるのではないでしょうか?
法人化することにより更なる事業展開が見込めるとはいえ、実際踏み出すのに不安もあるかと思われます。
法人化することのメリットとデメリットを知らずして法人化への検討はできません。それを把握したうえで、各々法人化すべきかどうか判断して頂ければ幸いです。
今回は、法人化のメリットとデメリットについて触れ、更に建設業の切り替え手続きについて解説します。
法人化のメリット
まずは社会的信用を得ることができます。法人は個人事業主よりも社会的な信用度は高くなります。例えば企業との取引であったり、金融機関からの融資においても取引を行いやすくなります。
次に節税効果も見込めます。個人事業主の場合は所得税として課税されますが、法人の場合は法人税の課税となります。現行の税制は所得税より法人税の税率が低くなるため節税効果が期待できます。更に法人は有限責任であるため業務上の債務は個人ではなく法人に帰属されます。そして株式(株式会社の場合)の譲渡などにより、事業承継が比較的容易であることがメリットといえます。
法人化のデメリット
法人設立には費用がかかります。株式会社か合同会社でかかる費用は異なりますが、費用や手続きに時間を要します。また設立後は税務会計処理が複雑になり、税理士等の専門家への依頼が必要になってきます。また建設業法改正により令和2年から適切な社会保険の加入が義務付けられました。これは建設業界に限ったことではありませんが、健康保険、厚生年金、雇用保険等の保険料の負担があります。
全ての事業主の方々が法人化に適している訳ではありません。皆さんの売上、経営方針、資産、家族構成等、総合的に勘案して法人化を検討していく必要があります。
法人化による建設業切り替えの手続き
次に法人化による建設業切り替えの手続きについて解説していきます。
大きく分けて2つの方法があります。
1.個人事業主の建設業許可を廃業し、法人設立後に新規で建設業許可を取得する方法
2.個人事業主の建設業許可を法人に継承させる方法
1は従来からある一般的な方法です。この方法では個人事業主の建設業許可を廃業するために、管轄の行政庁に廃業届を提出します。その後に法人を設立し、設立した法人名義で、新たに建設業許可の申請を行います。新規申請となるため、改めて許可要件を満たしているか審査されます。この方法だと一旦、建設業無許可期間が生じてしまう為、500万円以上の(建築一式工事1,500万円以上)の工事を請け負うことが出来ません。ただし、許可があった期間の工事は、注文者の了承があれば、完成まで継続できます。また、許可番号が変わってしまう為、ホームページの修正作業等も生じ、新規申請手数料等の費用が再度かかります。
2についてですが、これは令和2年の建設業法改正により新設された制度で、一定の要件を満たすことにより、個人事業主の許可を法人に引き継ぐことができるようになりました。
今までは個人の建設業許可を廃止し、法人設立後に新規で許可を取得しなければなりませんでした。しかしこの改正により事前に認可を受けることで、無許可期間を発生させずに軽微な工事を超える工事でも継続して請け負うことができます。許可番号も引き継がれ、新規手数料もかかりません。
手続きの流れについて
・事前認可の申請
法人設立前に管轄の行政庁に「譲渡及び譲受け認可」申請を行います。これは法人への承継発生日の1ヶ月前までには申請を完了させておく必要があります。
・事業譲渡契約の締結
個人事業主と法人間で、建設業に関する事業譲渡契約を締結します。
・法人設立・移行
法人設立、移行の手続きをします。
・認可取得
行政庁から認可が下りれば、法人は個人事業主の建設業許可を継承できます。
ここで、「許可」や「認可」という言葉が出てきてややこしいですね。厳密な定義は異なるのですが、ここでは行政庁からの了承と思って頂いて良いです。
基本的には、無許可期間が生じない「承継」の制度を検討することをおすすめしていますが、承継には厳しい要件があり、事前の準備と行政庁との綿密な相談が不可欠となります。
当事務所では法人化についてご相談を承っています。お気軽にご連絡下さい。
お問い合わせは↓ここから
お問い合わせ