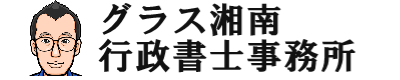宅建業免許とは?取得のメリットとデメリット

宅建業免許とは?
宅建業の免許を取得することによって、宅地や建物等の不動産取引を「業」として行うために、国または都道府県知事から受ける必要がある免許のことをいいます。
宅建業免許取得を検討されている方は、是非メリットとデメリットをご理解いただき、今後の宅建業免許取得の参考にして下さい。
メリット
・宅建業を営むことができる
宅建業免許を取得することによって、不動産の売買、交換、賃貸の代理・媒介を事業として行うことができます。つまり、これらの行為を業として反復継続的に行うことができます。無免許で宅建業を行った場合は、宅建業違反となり、懲役や罰金などの罰則が科されます。宅建業免許を持つことで、売買仲介、販売代理、賃貸管理など、幅広い不動産取引に携わることできます。
・社会的な信用が高まる
取引先や顧客は、宅建業免許を持っているという事で、一定の基準を満たしていると判断し、社会的な信用が高まります。宅建業免許は取引をする場合、必ず必要な免許となります。
・金融機関からの評価
不動産事業は取引額が大きいため、銀行融資などを活用することが多々あります。宅建業免許が事業の信頼性を示す一つの指標となるため、金融機関からの融資審査において高い評価が得られます。
・保証協会への加入で保証や他の加入業者との情報交換がある
宅建業免許を持つ事業者は「全国宅地建物取引業協会連合会(全宅連)」や「全日本不動産協会」といった保証協会に加入することができ、比較的安価な弁済業務保証金分担金の納付で開業できます。また最新の法令情報や業界動向に関する研修会、各種セミナーなどが開催され、常に新しい知識をアップデートし、他の加入業者との情報交換ができるというメリットがあります。
デメリット
・事務所の設置、維持費等
事務所を賃貸する場合は事務所探しが必要であり、免許要件に合致した物件を探す必要があります。また賃貸では毎月の賃貸料がかかり、自己所有でも賃貸でも事務所の維持費が発生します。
・免許申請後の更新手続き、費用がかかる
新規申請時はもちろん、申請後の更新時にも手続きの手間や更新費用がかかります。また、更新申請は5年ごとに行わなければなりません。
・営業保証金の供託または保証協会への加入費用
宅建業者は営業保証金を供託するか、宅地建物取引業保証協会に加入かいずれかを選択しなければなりません。営業保証金は高額で主たる事務所につき1000万円、その他の事務所につき500万円の供託が必要です。
一方保証協会に加入する場合は、弁済業務保証金分担金を納付します。主たる事務所は60万円、その以外の事務所は30万円で入会金や会費を含めると100万円程度の初期費用がかかります。初期費用を抑えられることから、営業保証金の供託より、保証協会への加入を選択している業者が大半を占めます。
・宅建業法の規制と義務
宅建業免許を取得すると宅地建物取引業法に定められた規制や義務を遵守する必要があります。法令順守はもちろんのこと、専任の宅建士の設置義務、各種書類の作成や保管義務など様々の制約を受けることになります。違反すると、罰則や監督処分の対象となります。
宅建業免許は賃貸アパートの大家さんの様に、自己所有の物件を自ら貸す行為は宅建業に該当せず、免許は不要です。しかし「不特定多数の者に反復継続」して売買、交換、賃貸の代理・媒介を業して行う場合は宅建業法が必要となりますので、不動産取引を業として行う場合は、必ず必要となりますのでご注意下さい。
当事務所では宅建業免許の取得に向けた、書類作成、申請を代行を承ります。お気軽にご連絡下さい。
お問い合わせは↓ここから
お問い合わせ