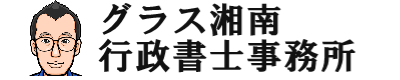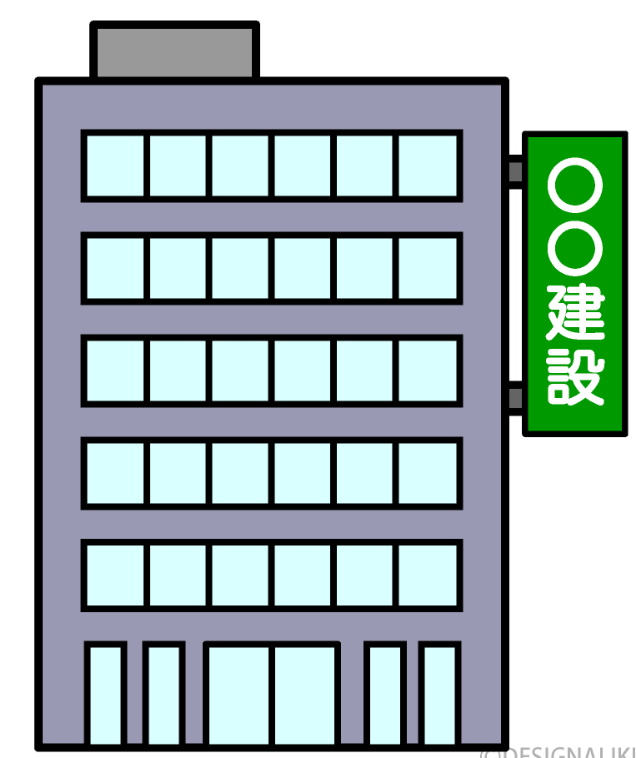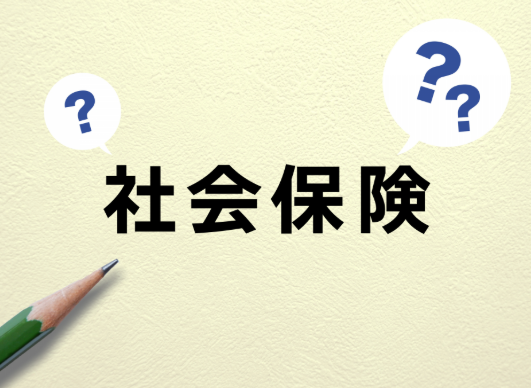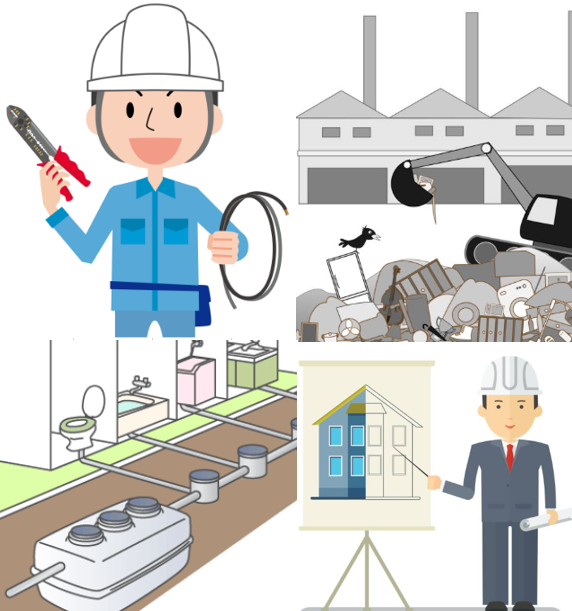「許可不要」に待った!軽微な建設工事と許可の関係性

建設業に携わっている方、またはこれから建設業を始めようしている方にとって、「建設業許可」の取得検討に頭を悩ませている方も多いのではないでしょうか?
今回は建設業許可が不要さとされる「軽微な工事」の範囲と、許可不要とすることでの潜在的な危険性について掘り下げていきます。
建設業法では「軽微な工事」のみを請け負う場合は許可が不要とされています。「軽微な工事」とは1件の請負代金が500万円未満(建築一式工事の場合は1,500万円未満)の工事、または建築一式工事で、延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事が軽微な工事に該当します。
「軽微な工事」については、前記コラムで触れた内容です。読まれていない方はそちらもご参照ください。→建設業許可とは?種類とメリット
しかし、この「軽微」を誤って解釈してしまうケースがあります。例えば以下のようなケースが考えられます。
請負金額に対する認識不足
請負金額の範囲には注文者が資材を支給する場合であっても、請負金額に含まれます。例えば、請負金額が200万円であっても建築資材が300万円の場合は合わせて500万円以上となるため、建設業許可が必要な工事となります。
また、軽微な工事の請負金額にも消費税が含まれます。極端な例ですが、税抜き499万円の工事でも消費税を含めると500万円以上となり、建設業許可が必要な工事になりますので注意が必要です。
追加工事による金額超過
よくあるケースとしては、請負契約当初は「軽微な工事」として請け負ったものの、状況の変化等により追加工事が発生してしまうケースがあります。結果的に請負金額が追加工事を含めると500万円を超過してしまうことがあります。
同一現場による複数の請負契約の判断
複数の契約が、物理的に連続した一つの建築物や施設の建設・改修を目的としている場合や複数の契約の工事が同時期に、または連続して行われる場合などです。
建設業法では、無許可で高額な工事を請け負うことを防止するため、請負金額の合計額で許可要否を判断します。契約を分けたとしても、実質的には一つの工事とみなされる場合があります。
以上のようなケースを誤って解釈し、意図せず法令違反を犯してしまうリスクがあります。
この様なケースが発覚した場合、3年以下の懲役または300万円以下の罰金、あるいはその両方の罰則が科される場合がありますので注意が必要です。
軽微な工事を主とする事業者の方も、下記事項に一つでも当てはまれば許可取得の検討をおすすめします。
・元請先から建設業許可取得をすすめられている。または発注要件とされている。
・より金額の大きな仕事を受注したい
・金融機関からの評価が向上し、資金調達をしやすくしたい。また社会的信用を向上したい。
・今後、元請け企業として活躍したい。
当事務所では建設業許可についてのご相談を承ります。お気軽にご連絡下さい!
お問い合わせは↓ここから
お問い合わせ