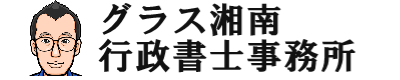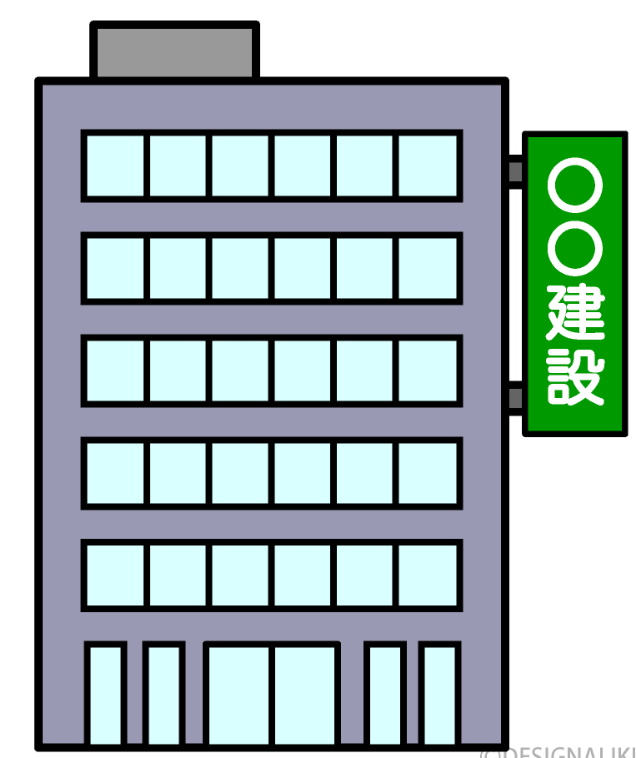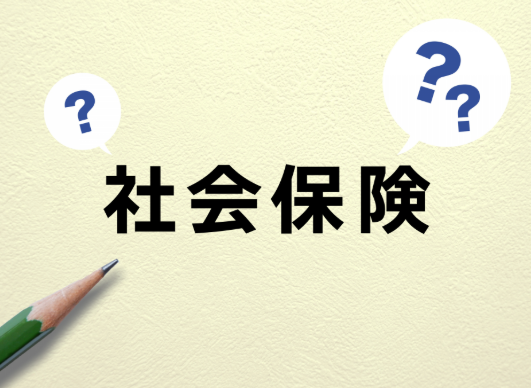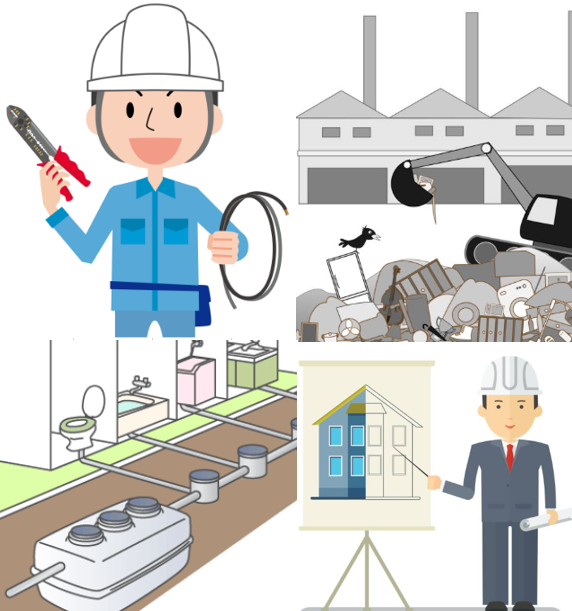技術者の兼任に関する緩和について

専任技術者と現場技術者の「専任」が求められる工事では原則、他の現場を兼任することは禁止されています。原則といったのは例外があり、それは同一場所または近接した場所で施工される、密接な関係にある2つ以上の工事の場合は、兼任が認められます。
令和6年12月の改正で、技術者の兼任に関する要件が緩和されました。また、呼称も変更され「専任技術者」は「営業所技術者等」に変わりました。
特に「工事現場間の距離」に関しては具体的な要件が明記されました。これは単に「近い」という事ではなく、現場管理に支障がないことを数値基準で示すことです。この改正により技術者の兼任がより柔軟に行えるようになり、人手不足の問題や生産性の向上に寄与することが期待されます。
今回は兼任の5つの要件について触れていきます。
要件① 建設工事の請負代金額の上限
要件② 兼任できる現場数
要件③ 工事現場間の距離
要件④ 3次下請を超えないこと
要件⑤ 連絡員の配置
要件① 建設工事の請負代金額の上限
改正前においても、建設工事の請負代金額の定めはありました。令和7年2月の改正で、専任が必要な工事は現場技術者の場合、請負代金4,500万円以上(建築一式工事は9,000万円以上)でした。令和6年12月の改正により、兼任する各建設工事の請負金額が1億円未満(建設一式工事の場合は2億円未満)に変更となりました。但し、工事途中で請負代金が1億円(建築一式工事の場合、2億円)を超えてしまう場合、それ以降は主任技術者又は監理技術者を専任で配置しなければなりません。
要件② 兼任できる現場数
「営業所技術者等」と主任技術者又は監理技術者である「現場技術者」で、兼任できる現場数が異なります。「営業所技術者等」は兼任できる現場は1工事現場となります。一方、「現場技術者」は2工事現場までとなります。営業所技術者は現場に出ることが原則出来ません。しかし、法改正により1つの現場の主任技術者として兼任することが認められるようになりました。この営業所技術者は複数の現場を兼任するのではなく、あくまで1つの現場までとなります。現場で複数の管理を同時に負うことは困難であるためです。一方、現場技術者については2つの現場まで兼任できるようになりました。現場技術者の役割は現場での施工管理です。後述する連絡員等によるサポート等で複数の現場を効率的に管理できるという考えにより、兼任が2現場まで認められるようになりました。
要件③ 工事現場間の距離
工事現場間の距離については営業所(工事現場)から他の工事現場間において、1日で巡回可能かつ移動時間が概ね2時間以内と定まられました。1日に巡回可能というのは片道に要する時間が2時間以内で判断されます。往復でも4時間以内となり、1日で巡回可能となります。またこの移動時間は当該工事に関し、通常の移動手段(自動車など)の利用を前提に、確実に実施できる手段により行います。極端な話、飛行機や新幹線の時間は対象としていません。今や新幹線で東京から大阪まで約2時間で行けますので、これでは確実に実施できる手段とは言えないでしょう。
要件④ 3次下請を超えないこと
当該建設業者が注文者となった下請契約から下請次数が3を超えていないことが要件となります。但し工事途中で、下請次数が3を超えた場合、以降は主任技術者又は監理技術者を専任で配置しなければなりません。
要件⑤ 連絡員の配置
連絡員とは発注者と元請け業者など、工事関係者との連絡・調整を行う担当者のことです。建設業法改正によって「連絡員」という名称が位置づけられました。
連絡員は特に資格などはないのですが、営業所主任者等の実務の経験として認められる経験を想定しています。技術者が不在となる現場に配置が義務付けられているのが連絡員です。連絡員は、技術者からの指示を現場に伝えたり、現場状況を技術者へ報告する役割を担います。
連絡員は各工事現場に置く必要があります。なお、同一の連絡員が複数の工事現場を兼務することは可能です。連絡員には工事現場での専任や常駐は求められておらず、雇用形態においても問われません。但し、連絡員の配置義務は当該請負会社が負いますので、施工管理の最終的な責任は請負会社が負うことになります。
当事務所では建設業許可に関する、ご相談を承ります。お気軽にご連絡下さい。
お問い合わせは↓ここから
お問い合わせ